児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。2012年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
児童扶養手当と公的年金等の併給が可能になりました
これまで、公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当は受給できませんでしたが、2014年12月からは、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できるようになりました。
新たに手当を受け取れる場合
- 子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
対象になる人
手当を受けることができる人は、次のような条件に当てはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度の障がいがある児童の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人です。
- 父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合も含みます)
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度まで)
- 父(母)が3カ月以上生死不明である児童
- 父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
- 父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
- 父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
対象にならない人
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 父、母または養育者が、婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
支給額(月額) (R7.4月~)
児童が1人のとき
- 全部支給: 46,690円
- 一部支給: 11,010円から46,680円まで(所得額に応じて決定されます)
児童第2子以降について
■第2子以降のお子さんについては、第1子の金額に下記の金額が加算されます。
- 全部支給:+11,030円
- 一部支給:+11,020~5,520円
認定請求のしかた
直接窓口で認定請求をしてください。
請求場所
保健福祉課 福祉班
受付時間
8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
必要なもの
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童が記載されているもの)
→ 本籍が野田村にある方は、提出は不要です。 - 請求者本人名義の預金通帳
- 印鑑(認印可)
(注意)その他、必要書類等ありますので、詳しくは直接お問い合わせください。
手当の支払い
手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。遡って支給することは出来ませんのご注意ください。
支払いは指定した金融機関へ口座振込で行われます。
手当の支払日
- 5月9日(3月分、4月分)
- 7月11日(5月分、6月分)
- 9月11日(7月分、8月分)
- 11月11日(9月分、10月分)
- 1月9日(11月分、12月分)
- 3月11日(1月分、2月分)
(手当の支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日が支払日となります)
現況届
現況届は毎年8月1日時点における状況を届けてもらうことで、児童扶養手当を引き続き受給できるかどうか確認するものです。毎年8月に現況届用紙を送付し、8月中に提出していただきます。提出がないと8月分以降の手当を支払いできません。
所得制限について
手当を請求する本人または扶養義務者の所得が一定額以上のときは、手当額の全部または一部の支給を停止します。扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の所得も算定対象となります。(扶養義務者とは、申請者本人と同じ住所に住む直系親族(父母・祖父母・子など)および兄弟姉妹をいいます)
|
扶養人数 |
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
| 所得ベース | 所得ベース | |
| 0人 | 69万 | 208万 |
| 1人 | 107万 | 246万 |
| 2人 | 145万 | 284万 |
| 3人 | 183万 | 322万 |
| 4人 | 221万 | 360万 |
| 5人 | 259万 | 398万 |
- 申請時期が1月から9月までの場合、前々年の所得を確認します。
- 申請時期が10月から12月までの場合、前年の所得を確認します。
その他
- 村内で転居された場合は、住所変更が必要となりますので窓口までお越しください。
- 転出される場合は、手続きが必要となりますので窓口までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班(保健センター)
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





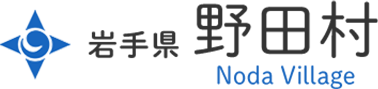



更新日:2025年04月21日